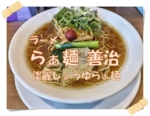【読書】『統合失調症』

脳科学の進展により、分からなかったことが分かるようになってきた。統合失調症は、およそ百人に一人が罹患することになる、頻度の高い、身近な疾患である。にもかかわらず、多くの人にとっては、まだ縁遠く不可解な疾患でしかないのが現状である。
統合失調症を理解するためには、正しい知識とともに、人間として共感することが大切に思える。統合失調症にかぎらず、人間関係の基本なのではないかと思う。
劣悪な環境に放り込まれたら、妄想でも空想でも逃げ道を探し出したいだろう。まとめて同時に十人に話しかかられたら、まとまる考えも纏まらないが、注意力が散漫になり、ミスも増える。いじめでもハラスメントでも受け続ければ、誰だって活動性は低下する。
人間が人間として、当たり前の対応をすることが大切なのは、統合失調症の患者ばかりでない。
ある意味では、ままならない現実に対して、妄想にすがりつくことでバランスを保っているのだ。それに、幻聴や妄想のような症状があっても、社会で問題なく生活できている人はたくさんいる。
治療も大きく様変わりしている。しかし、一方で、回復が頭打ちになってしまう状況も見られる。そこには、病気という視点だけでは克服できない問題もある。
症状
統合失調症ではさまざまな症状が見られるが、大きく二つに分かれる。
陽性症状:幻聴、独り言、妄想、興奮
陰性症状:活動性、意欲、関心の低下
また「解体症状」と呼ばれる、行動や言語の纏まりが悪くなる症状が見られる。根底にあるのは思考の混乱である。考えがうまく纏まらなかったり、論理的な筋道に沿って話を進めることができなかったりする。
近年では「陽性症状」「陰性症状」とは別に「認知機能障害」も注目されている。認知機能とは、「注意力」「作業記憶」「言語的能力」「視覚、空間的能力」「統合能力」「実行機能」「社会的認知」など多面的な能力で、相互に関係している。
認知機能のどの働きが低下しているのかを理解した上で、リハビリや訓練を行っていくことが必要になる。
とくに関心が集まっているのは「注意障害」である。注意の機能には「検出」と「分類」という二つの働きがあり、どちらか片方の感度を高めると、他方の感度が落ちるというジレンマがある。統合失調症の人は、このバランスが悪いのである。はるかに少ない情報量でも過負荷を生じやすい。
また「過敏性」のために、集中できなかったり、特に意味のない些細な出来事にも傷ついてしまう。
【解体型】
纏まりの悪さと、常識的な世界が崩壊し、意味を共有しあうことが困難な状態。
周囲に対する無関心や引きこもりが見られるのは、過敏すぎるがゆえに、外の世界と関わるのが負担で苦痛になってしまうからだ。
安心感を与え、関心や自信を引き出すことが大切である。
【緊張型】
激しい興奮とまったくの無反応な状態が、急激に出現する。
症状は激しいが、治療が成功すると比較的速やかに回復する。
【妄想型】
妄想や幻覚。妄想が体系的なストーリーを持っていることが多い。
妄想は本人にとって心地よい心の支えとなっている。
妄想を取り除こうとすると失敗する。現実生活の中で自らの役割を見出す方が上手くいく。
遺伝子・脳科学
ナチズムは、反ユダヤ主義を掲げたが、その科学的な根拠は遺伝学や優生学である。ナチスの「民族浄化」の犠牲になったのはユダヤ人ばかりでなく、統合失調症の患者も犠牲になった。直接的に抹殺したのはナチスだったが、日本もアメリカも優生保護法による去勢手術や堕胎という形で間接的に行っていた。
今日の遺伝学からすれば、統合失調症の原因となる遺伝子は、一つではなく二つ以上の遺伝子が関わっている。また、遺伝子変異は、特別なものというより多くの人がもち、人類の多様な個性や特性を生み出すのに役立っている。
ナチスの残虐な行為が明らかとなると、遺伝学などの生物学的精神医学は急速に人気を失い、心理学的精神医学に舵が切られる。
生物学的精神医学が復権したのは、クロルプロマジンの登場だった。ドーパミンが結合するD2受容体を遮断する作用がある。
こうして薬物療法が治療の中心として発展することになる。
統合失調症のベースには、脳の機能的障害がある。最近の診断技術の進歩により、分からなかったような異常が脳に起きていることが分かった。
病気の進行とともに脳が縮んでいく。また、神経線維の走行の乱れが見られる。適切な治療を行わないと、じわじわと進行し、機能の低下をきたしてくる。
よって、早期発見も重要になるが、再発防止も重要になる。
現代では、すぐれた抗精神病薬の登場により、服薬を続け、過度なストレスを避け、バランスよく過ごせれば、良好な予後を得られる。
過敏性は脳波や神経細胞レベルでも観察できる。
予め刺激を与えておくと、次に刺激を与えられたとき反応が抑えられる「プレパルス抑制」が、極端に低い。
また、海馬が興奮を起こしやすい。GABA介在ニューロンの放出で興奮を抑制する「前シナプス抑制」と呼ばれる働きが弱い。
過敏性による興奮のしやすさは、纏まりの悪さ、妄想的認知、注意障害の原因と考えられる。
統合失調症があるとニコチン依存になりやすい。ニコチンはドーパミンなどの伝達物質を放出させる。しかし、それは一時的なことで、すぐに感受性を失い反応しなくなる(脱感作)。感受性を失うことが興奮を鎮めてくれるので、思考の纏まりがよくなったり、幻聴を減らしたりもする。現在では、ニコチンのように効果がすぐに薄れることもなく、有害な副作用のない薬剤の開発が進められている。
環境とライフスタイルを整える
一つの遺伝子変異があった、あるいは不利な遺伝子が重なっていたとしても、発症することよりも、発症しないことの方が多いのである。
発症するか否かは、環境的な要因が関わっている。多くの人は知らずに過ごしているのである。
発病しやすい体質に、環境からのストレスが加わることによって、発症に至る「脆弱性―ストレスモデル」が用いられる。発病しやすい素因が強ければ、些細なストレスでも発症することはある。しかし、その素因も遺伝的に決定されるのではなく、後天的な要因によって形成される。ストレス耐性そのものが、環境に依存しているのである。
近年、国家レベルでデータが整備されるとともに「統合失調症は、世界のあらゆる地域で、ほぼ均一に認められる」という前提自体が揺れている。厳密な研究によって、少なくとも五倍の地域差があることが判明している。
先進国では、貧しい階層で有病率が高いが、新興国では裕福な階層に多いという。先進国では回復が遅れ、新興国では予後が良い。ワーナーの考えは、新興国では、賃金のためではなく、生活の一部として仕事をしているからだと考える。
その人ができそうな仕事を見つけて与える、という融通が利く。つまり、過度な負担やプレッシャーを感じることなく、病状に応じた仕事をすることができる。それが回復に非常に有利に働く。プロイラーは
「規則正しい仕事は正常な思考を維持する」のに役立つが、叱責や過度の負担といったストレスは仕事に対する喜びを失わせるとして、ほどよい負担に調整することが大事だとした。これは、統合失調症の患者ばかりではないように思える配慮なのではないだろうか。
劣悪な環境において薬でごまかす、では状況が悪化するだけである。
家族や集団が、病状を本人の欠陥として非難したり排除したりするのではなく、みんなの問題として受け止め、受け入れることが非常に重要なのである。
とはいっても、現代の労働環境は過酷なものになっている。病気になるか、過労死するか、失業か、である。もっと中間の、バランスの取れたライフスタイルを送れるようにできることが理想なのだ。
それに、年金や生活保護だけでは解決しない。経済的な不安は取り除けるが、精神的な生き甲斐や自分の存在価値は感じ取れない。
バランスの取れたライフスタイルを送れるようにすることが、発症を防ぎ、予後を改善し、それが結局は社会のためになり、めぐりめぐって自分のためにもなるのだ。
治療と回復
統合失調症は、気づく前に認知機能障害や陰性症状が進行し、脳の萎縮が始まっている場合がある。無治療の期間が長いほど、脳はダメージを追ってしまう。そうならないためにも、早期発見と治療開始が重要になる。
統合失調症の過敏さは、単に敏感であるという域を超えている。接するうえで、本人の脆い安心感を極力脅かさないようにすることが大切である。
個性の強いスタッフや気性の激しい親が熱心にかかわると、逆効果である。
また、非難したり、人格を否定したりするような言い方も、よくない。
治療の信頼関係に確立と維持も重要になる。
急性期には安心を与える。本人を否定せずに、よくなっているところを肯定するのである。
回復期でも焦らないこと。本人もそうだが、支える側も急かしてはならない。
重要なのは、安定期を長く支えることである。日常とは、単調な繰り返しの中で、ささやかな喜びを見つけていくことである。いつも進歩や向上を求めてしまうと、無理をしたり追い詰めてしまう。
また、人とは何らかの形で誰かの役に立っていることで、自らの存在価値を確認するものである。現実の中に存在価値を見出せなくなれば、妄想の中に逃げ込んでしまう。
ロンドン精神医学研究所では、統合失調症の患者の家族の感情表出の強さによって「高EE家族」と「低EE家族」に分けた。「高EE家族」の方が再発率が高かったのである。「高EE家族」を判定する基準は、
- 批判的言動が多い
- 本人に対する敵意がみられる
- 情緒的に巻き込まれている(過保護や自己犠牲的な献身、強すぎる思い入れ)
であり、最悪のものは「敵意」である。
過干渉にならないように、本人の主体性を尊重し、否定的な言い方を慎み、厄介者扱いするような言い方やプライドを傷つけるような言い方は避けたい―――――
―――――と書いてみたのだが、程度の大小こそあれ「個性の強い人」や「気性の激しい人」は、なんとなく敬遠したくなるものだ。
非難の言葉や人格否定の言葉を投げつけては、仲良くなれるはずもない。
向上心を否定するわけではないが、どこかで休息をとらないと、いずれ破綻する。
友情とは信頼関係の確立だと思うが、世の中には、そんなことを考えない人がいる。
熟練の精神科医のような対応はできないかもしれないが、差別的な言動をやめることはできる。人生も、ここまでは頑張るが、ここからはゆとりをとる、というライフスタイルも可能な範囲でやればよい。
結局は「他者に対する人間的対応」ができるか否かなのだが、それは統合失調症の患者にかぎらない。自分だってそうしてもらいたいと思えば、他者に対してもそう振舞えるはずである。
技術進歩により、薬物療法で苦労することが減り、スムーズに改善するケースが増えている。よって、きちんと服薬することである。
決まった日課や仕事に取り組んだ方が、改善や安定に寄与することは、上述した。
ほどよい引きこもりは、過敏な人の過剰な神経興奮を防ぎ、安定化に寄与する。誰しも、たまには一人になってみたい、と思うことはあるだろう。
認知機能障害の程度が予後に最も影響を与える。軽度なケースほどリハビリの効果が高いのだが、軽度なほどリハビリを受けていないジレンマがある。
作業療法やデイケアなどを活用したほうがいいが、趣味や創造行為、表現行為も安定に寄与する。
なによりも、ライフスタイルや価値観を見直すことである。病気になる前と同じ生活をしても、失敗を繰り返すだけである。同じ失敗をしたくなければ、やり方を変えるしかない。
向上心や目標に向かって頑張ることを否定するわけではないが、それも程度の問題である。どこかで線を引き、ゆったりと人生を味わい楽しむ方にシフトチェンジすることである。