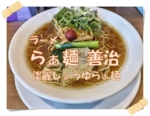【読書】『十字軍物語』第一巻【乱れている国同士が戦うとどうなるか?】

「乱れている国」と「治まった国」という戦いなら、「治まった国」が勝つ。乱れている国が治まった国を攻めると滅びる(中略)『韓非子』 金谷治訳注 岩波文庫
では、「乱れている国」と「乱れている国」が戦ったらどうなるか?
「十字軍」と「イスラム勢力」は、国家間の戦争ではないんだけど、十字軍側も、イスラム側も、どちらもバラバラでした。
その「バラバラな人たち同士が戦うとどうなるの?」という物語から、教訓を拾い出してみよう。
- 憎まれるようなことをするな。
- 「究極の目標」を思い出し、一時的に手を組もう。
- 「白黒思考」のワナにはならないようにしよう。白と黒のあいだには、さまざまなグラデーションがある。
第一次十字軍の流れ
皇帝と教皇の争いの「とばっちり」
1077年 カノッサの屈辱。
皇帝の行った人事に対して教皇が反対したことから始まった事件。
皇帝ハインリッヒが雪の中で許しを請うことで、教皇と教会の権力が勝利した―――――
その後の展開を、世界史の教科書は書いてくれなかったので、まったく知らなかった。
怒り狂った皇帝ハインリッヒは、教皇グレゴリウスを追いつめることで、教皇と教会の権威は地に落ちる。
衆人の前で屈辱を与え恥をかかせるのは利口なやり方ではないその後の教皇も教会もやられっぱなしだったのですが、うまいことを思いついたのはウルバン二世。
「神が望んでおられる」
そういって第一次十字軍を提唱。
神が望んでおられる十字軍は、
イェルサレム奪還して、成功し、
神への信仰心、キリスト教への信仰心を盛り上げ、
教皇と教会の権威を上昇させ、
それに逆らった、皇帝ハインリッヒの権力が地に堕ちる
ということで、皇帝ハインリッヒの晩年は、臣下どころか子どもたちからも相手にされなくなることに。
「この恨み、晴らさで置くべきか!」
という気持ちは分かりますが、やりすぎるとやり返されるから、自分が困ったことになる。
軽蔑されることと憎悪されることとは君主が警戒すべき事柄『君主論』第16章
人に危害を加える場合には、復讐を恐れなくて済むような仕方でしなければならない。『君主論』第3章とにもかくにも、皇帝と教皇の争いが発端の十字軍。
攻め込まれたイスラム教徒や中近東の方々にとったら「とばっちり」以外の何物でもない。
まとまりがない第一次十字軍
そんな理由から始まったので、第一次十字軍に、当然のことながら皇帝は不参加。
司令官に皇帝を据えることができないので、フランス王を指名したいところ。しかし、そのフランス王も、不倫相手と結婚したくなって、離婚したいとお願いしたら、教皇に破門されている。よって、フランス王も不参加。
ということで、第一次十字軍は「諸侯たちの十字軍」になる。
最後まで最高司令官不在のままだったので、指揮系統の一元化など望むことはできず、てんでバラバラ。
しかも、ケンカしてばっかり。
十字軍側のバラバラさを箇条書きにすると、
- 諸侯間の争い
- 聖職者、騎士、商人の対立
- ビザンツ皇帝の狡さ、せこさ、利己主義、による非協力
- カトリック、ギリシア正教徒、アルメニア宗派のキリスト教徒の対立
ここまで書くと、なぜ成功したのかが理解できなくなる。
対するイスラム勢
理由は、イスラム教徒も乱れていのである。
- 各領主間の争い
- トルコ人、アラブ人、その他少数民族の対立
- エジプトのカリフとバグダッドのカリフの対立
- スンナ派とシーア派の対立
イスラムの年代記作家も嘆くことになるのだが、十字軍にまとまりがないのなら、イスラム勢にもまとまりがなかったのである。
十字軍の勝因
というのが、塩野さんの評。彼らは、ときに、いやしばしば、利己的で仲間割れをくり返したが最終目標の前には常に団結した。この点が、利己的で仲間割れすることでは同じだった、イスラム側の領主たちとのちがいであった。そして、それこそが、第一次十字軍が成功した主因なのである。
キリスト側は「聖地奪還」という「究極の目標」で一時的に手を組んだだけに過ぎない。
対して、イスラム側は究極の目標をもてず、自己の利益しか考えられず、ゆえに手を組めなかった。
第一次十字軍から得られる教訓
憎まれるようなことをするな
マキアヴェッリですら言っている。
「憎悪されるな」
「復讐を恐れなくて済むようにしろ」
パワハラ、モラハラ、カスハラなんて言うけれど、どれをとっても、恨まれて憎まれるだけ。
やり返されたらどうするのか?
モラルやマナーの観点からでも問題なのに、戦略としても問題がある。
憎まれるようなマネだけはやめよう。
「究極の目標」を思い出し、一時的に手を組もう
十字軍の「究極の目標」は「聖地奪還」だったのですが、そうれなら、イスラム勢の「究極の目標」は「防衛」で良かったのです。
教皇、神聖ローマ皇帝、フランス王、ビザンツ皇帝も、「究極の目標」を思い出せばよかったものを。
白黒思考のワナにはまるな
そもそもの疑問、「乱れている国」と「乱れている国」が戦ったらどうなるのか?
これは「白黒思考」のワナにはまっていたのです。
世の中には、「治まっている国」と「乱れている国」しかないと、安直な二分法で考えたから、分析できなくなっている。
『ファクトフルネス』的に言うと、「分断本能」。
白と黒のあいだにはさまざまなグラデーションがあることを忘れないようにしよう。
第一次十字軍の場合、「乱れている国」にもグラデーションがあり、二つに分けることができる。
「一時的に手を組める国」と「一時的ですら手を組めない国」に。
まとめ
- 憎まれるようなことをするな。
- 「究極の目標」を思い出し、一時的に手を組もう。
- 「白黒思考」のワナにはならないようにしよう。白と黒のあいだには、さまざまなグラデーションがある。