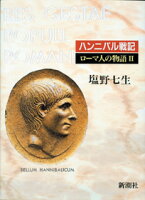【君主論】愛されるよりは恐れられる方がマシだ【ただし、「誤用」に気をつけて】

『君主論』第一七章は「残酷さと慈悲深さとについて、敬愛されるのと恐れられるのとではどちらがよいか」である。
「慈悲深さ」を誤用するな
マキアヴェッリは「慈悲深さ」を「誤用」して例として、フィレンツェ人がピストイアを破壊したを挙げている。
分かりやすくするなら「犯罪」に対する「刑罰」であろう。
誰だって―――犯罪者ですら―――自分が殺されることも、傷つけられることも、奪われることも、嫌なことである。
それを防ぐために、「刑罰」がある。
「刑罰」の実行そのものは「残酷さ」であるが、社会不安を一掃するための抑止力として考えたら「慈悲深さ」である。
社会不安を一掃し、共同体の安全を守るため、そして『君主論』ではそうやって君主権を安泰なものとするため、「残酷さ」を有効活用しなければならない。
私見によれば、各君主は慈悲深く、残酷ではないという評判をとるように望むべきではあるが、しかしこの慈悲深さを誤用しないように注意しなければならない。マキアヴェッリは、「残酷さ」を有効活用した例に、チェーザレ・ボルジアを挙げている。
チェーザレに関しては、こちらの本が詳しい。
チェーザレが、ロマーニャを回復し、統一し、平和を実現したのは、「残酷さ」を有効活用したからだ。
よって、マキアヴェッリは、
支配者は自らの臣民の団結と自らに対する忠誠とを維持するためには残酷だという汚名を気にかけるべきではない。と結論する。
「残酷さ」も誤用してはならない
社会の安定に「残酷さ」を用いることを肯定している。
その一方で、こうも言っている。
人間は恩知らずで気が変わり易く、偽善的で自らを偽り、臆病で貪欲である。君主が彼らに対して恩恵を施している限りは彼らは君主のものであり、生命、財産、血、子供を君主に対して提供する。当時のイタリアは、なによりもマキアヴェッリの祖国フィレンツェは、混乱を極めていた。
”もし人間がすべて善人であるならば、このような勧告は好ましくないであろう”(第一八章)。
傭兵隊に関しては、”君主が戦争を行わない間のみ彼らは兵として仕えようとするが、いざ戦争になると逃亡するか、雲散霧消してしまうのである
”(第一二章)
第一七章では、
これはすでに述べたようにその必要が差し迫っていない場合のことであり、その必要が切迫すると彼らは裏切る。したがって彼らの言葉に全幅の信頼を置いている君主は他の準備を整えていないために滅亡する。
魂の偉大さや高貴さに基づくものではなく報酬で得た好意はそれ相応のものであって、手に持っていて必要な時に費やすようなことはできないからである。「魂の偉大さ」や「高貴さ」に関してはマキアヴェッリも肯定している。
人間は恐れている者よりも愛している者を害するのに躊躇しない。なぜならば好意は義務の鎖でつながれているが、人間は生来邪悪なものであるからいつでも自己の利益に従ってこの鎖を破壊するのに対して、恐怖は君主とつねに一体不可分である処罰に対する恐怖によって維持されているからである。この勧告は、
- 「慈悲深さ」を誤用しないため
- 「残酷さ」を有効活用するため
の心構えだ。
「恐れられること」と「憎まれないこと」は両立できる
マキアヴェッリといえども「憎まれるな」といっている。君主は仮に好意を得ることができないとしても、憎悪を避けるような形で恐れられなければならない。恐れられることと憎まれないこととは、恐れられることと愛されることよりも容易に両立しうる。このことは君主が市民や臣民の財産と彼らの婦女子に手を出さないならば、必ずや実現されると思われる。
参照:【君主論】「軽蔑」と「憎悪」を避けろ
そのために、民衆の財産や婦女子に手を出すな、と忠告している。
「婦女子に手を出すな」は当然として。民衆の財産に手を出さないためには「ケチになれ」とも言っている。
参照:【君主論】気前が良いより「けち」になれ【憎悪されるよりはマシ】
人間は財産の喪失よりも、父親の死のほうを速やかに忘れるものだからである。他人の財産の強奪によって生活し始めた者は、他人からそれを奪う口実を見つけ出すことになる。反対に命を奪う口実はあまりなく、その口実はより速やかに尽き果てるものである。民衆の財産に手を出したら、憎まれる。そして、あげくに軽蔑される。
それだったら、「ケチ」になって憎まれないほうがいい。
そして、国内の安定のために、「残酷さ」を有効活用する。
「恐れられないこと」と「憎まれないこと」は両立するのだ。
人間は自らの意に従って愛し、君主の意に従って恐れる。賢明な君主は自らの自由になる者に依拠すべきであって、他人の判断に依存してはならない。そしてその際すでに述べたように憎悪を招かないようにだけ配慮すればよい。
極端な例として「軍事行動」
”他人の財貨は蕩尽せよ”と第一六章で述べているように、軍事行動は極端なので分かりやすい。君主が軍隊とともにあって多くの兵士を統率する場合には、残酷であるという評判を全く気にする必要はない。
マキアヴェッリは、具体例としてハンニバルを挙げている。
現代でいえば、スペインから遠征をはじめ、フランスを迂回し、アルプスの山越えを行い、イタリアに攻め込んでいる。
その際、無数の人種からなる巨大な軍隊を率い、遠隔地で軍事行動をすることになったが、兵士は付き従った。
ハンニバルに関しては、塩野七生さんの本を読むことをオススメする。
というのが、マキアヴェッリのハンニバルの評。思慮のない著作家達は一方で彼の行動を称賛しながら、他方でそれを可能にした根拠を弾劾している。
一方、慈悲深かったために失敗した例としてスキピオ・アフリカヌスを挙げている。
ハンニバルを破り、戦争を終結させ、ローマに勝利をもたらし、イタリアに平和を取り戻した。
にもかかわらず。スキャンダルを悪用され、元老院に中傷され、そして隠遁に追い込まれた。
問題なのは「誤用」
『君主論』は君主権強化のため、君主の立場で言っている。しかし、社会不安の一掃と、共同体に平和は、誰にとっても必要で、望まれることだ。
「慈悲深さ」と「残酷さ」を比べると「慈悲深さ」を優先したくなる。
ところが、これが「政治」の場になると「慈悲深さ」は、かえって社会不安を招き、共同体に不穏をもたらす。
つまり「慈悲深さ」は「誤用」されやすい。
一方、「残酷さ」は、臣民を傷つけず、財産を奪わず、ようするに憎まれないようにすればいい。
これさえ気をつけていれば。「残酷さ」は「誤用」されにくい。
マキアヴェッリは、こう結論づける。
愛されるよりも畏れられる方がより安全である。「誤用」しやすい「慈悲深さ」よりも、「誤用」しにくい「残酷さ」のほうがマシなのである。